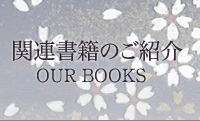
![]()
(編)野中郁次郎 嶋口充輝
価値創造フォーラム21
まえがき-新たなる経営の美学を求めて
5、アートとサイエンスの融合
米国を発祥の地とする経営学は、フレデリック・テーラーにはじまりハーバート・サイモンらの研究により、曖昧だった経営学の概念を精緻化し、科学的分析に基づくマネジメントの方法論を確立するという偉大な功績を残した。この米国流の科学的経営管理手法の成功は、その流れを受け継いだわが国でも主流となった。しかし、近年はこの科学的方法論に基づく経営にいくつかの批判が生じている。たとえば、マギル大学のヘンリー・ミンツバーグ教授は、経営とは経験(クラフト)、直感(アート)、分析(サイエンス)の三つを適度にブレンドしたものであり、「唯一最善の方法」などはないと、科学的経営を身上とする米国型MBA教育を批判する。
確かに、マネジメントの本質は無機質で合理的なサイエンスより、人間的、属人的なアートの面が大きい。科学的な視点による分析は確かに必要であるが、科学的方法をベースにした分析至上主義だけでは経営のリアリティがつかめない。現在は過去の積み重ねの上にあるが、経営の未来は不確実で合理的な分析のみでは解決できない。経営は、未来を考えて意思決定を行う局面が多くあることを考えれば、むしろその時々の状況において現象の背後にある本質を直観し、サイエンスとアートを融合して物事を実行する賢慮の能力が求められている。まさに科学合理性と人間的知恵をうまく組み合わせることであり、それは企業活動の理(ことわり)の確立と新しい経営の型の探求そのものになる。
知識をベースにするこれからの経営においては、新しい歴史観のもと、普遍・合理的なサイエンスの知見と人間の機微を優しく理解するアート的知恵が融合して、初めて未来を美しくする「経営の美学」が成り立つといえるだろう。ここにこそ、「こうありたい、こうあるべき」という精神的支柱に当たる経営ビジョンも意味を持つのである。